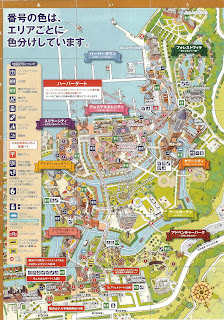<今月読んだ本>
1) 満州国演義(四、五、六、七)(船戸与一):新潮社(文庫)
2) 東京大学第二工学部(中野明):祥伝社(新書)
3) Hard Choices(Hillary Clinton):Simon&Schuter
4)老前整理(坂岡洋子):新潮社(文庫)
5)大格差社会アメリカの資本主義(吉松崇):日本経済新聞出版社(新書)
6)米軍式 人を動かすマネジメント(田中靖浩):日本経済新聞出版社
<愚評昧説>
1)満州国演義(四、五、六、七)
昨年10月の本欄(今月の本棚-86)で第3巻まで取り上げた同名の歴史小説のその後に出版された続巻である。一気に4巻まとめ読みした。前巻までの概要は、満州前史(1928)から、満州事変(1931)を経て満州帝国成立(1932)に至る、日本・中国・満州を巡る、政治・社会・国際関係・軍事を敷島四兄弟(太郎;奉天領事館勤務の外交官、次郎;中学卒業後満州に渡った馬賊の頭目、三郎;陸士出の憲兵将校、奉天駐在、四郎;学生時代左翼演劇に投じ、その後上海の東亜同文書院で中国語を学び、彼の地に滞在)とそれに絡む謎の多い特務機関員間垣徳蔵(今回中佐であることが分かる)の言動を通して描いたものであった。
今回も上記の5人がそれぞれの役割を演じながら、満州史・昭和史の大きな出来事と関わっていく。満州帝国成立により太郎はその外交部(外務省に相当)に移る。次郎は密告で配下をことごとく失い一匹狼として請負仕事で糊口を凌ぐ。三郎は憲兵大尉に昇進、満州から中国本土、蒙古と活躍の場を広げていく。四郎だけが相変わらず定職がなく、徳蔵つきまとわれながら、それでも北京官語・上海語を駆使できる才能を買われて、大陸のさまざまな場所で健気に奮闘する。
彼らに絡む歴史的事件は、第一次上海事変(1932)、国際連盟脱退(1933)、ナチス党政権成立(1933)とユダヤ人迫害(満州経由で大勢のユダヤ人が上海に流れてくる)、2・26事件(1936)、日独防共協定(1936)、盧溝橋事件から第2次上海事変(1937)、ノモンハン事件そして欧州大戦(1939)と激変し、満州から発した大陸の事変(局地戦)・事件は世界規模の争いに組み込まれていく。1940年三国同盟を契機に米英の締め付けは厳しさを増し、ついに1941年12月の真珠湾攻撃そしてマレー半島上陸で太平洋戦争が始まる。
4兄弟の役割と所在もこれらの事件と密接に関わり、太郎は満州国外務官僚として出世はしたものの実質は傀儡政権下で無聊をかこち、出番はせいぜいユダヤ人受け入れ問題くらい。かたや一匹狼になった次郎はインド独立を志す人々の支援を行いつつマレーからシンガポールに進出。三郎は上海・南京戦あるいはノモンハンでの軍紀取締りに当る。四郎は紆余曲折ののち嘗ての演劇経験を生かし甘粕理事長の下で満州映画のシナリオライターになっている。
主人公達個々の日常は完全にフィクションであるが、空間・時間・事件内容をこれだけ広くとりながら歴史をたどるのは容易なことではない。スケールの大きい物語ゆえに、著者が性格や職業の異なる4兄弟を主人公に据えた理由が分かってくる。さすが!とあらためて著者の構想力を見直した。
さて、史実との関係である。どこまでが事実なのかはいまやはっきりしないことが多い。作者は憲兵大尉の目を通して南京事件や731部隊を描くのだが、そのシーンはかなり凄惨なもので、フィクションと割り切っても私自身の歴史認識に何がしかの疑問を生じさせたことは確かである。それはマレー戦におけるインド兵の宣撫・反乱工作など、本欄でも取り上げた藤原岩市(陸大卒、陸自陸将)著「F機関-アジア解放を夢見た特務機関長の手記」の内容を明らかに引用しているところが多々あり、支那事変も相当調査を綿密に行った上でフィクションに仕立てていると見られるからである。
戦場の従軍慰安婦(強制徴発には触れていない)、日満官吏の格差(給料10:1)、満州・朝鮮における抗日ゲリラと対ゲリラ戦、満蒙青年開拓団の結婚問題(抽選で相手を決める)、長征の実態(完全な負け戦;逃避行を見事に覆い隠した宣教活動)、ドイツの国民党軍支援(第2次上海事変で苦戦したのはドイツ軍事顧問;ファルケンハウゼンの力)、英国財務顧問;リース・ロスによる幣制統一(地方・軍閥で異なる幣制だった)改革など、加えて全巻に溢れる日本陸軍の組織・統帥から個人に至る権力闘争・功名争い・思想対立・政治的専横。ことの軽重を問わず、真相を更に確かめてみたい話題が頻出する。
残るは2巻、いよいよ自分の生きてきた時代に移る。ここで少しでも記憶に残る体験で本書の検証が出来ると良いと思っている。
2)東京大学第二工学部
私が東燃に入社した時代(1962年)、専門分野である計測・制御・情報は比較的新しい技術分野だったこともあり、工学部の中に独立した学科を持つところはほとんど無かった(唯一慶大に計測工学科があり、東大の応用物理学科に計測工学コースがあった)。10月正社員になり、配属された工務部工事課の計器係・電気係担当課長は東大工学部機械科卒(昭和25年卒業;この人は単に管理職としての役割だけで、その分野の経験は全く無かった)。翌年7月工場技術部機械技術課に移ると今度の課長は東大造兵科出身という初めて耳にする学科だった。この人は計測制御畑から出ていたので、経歴に関心はあったが口が重く、会話は禅問答と言われていたので、なかなか気安く話が出来る人ではなかった。そこで飲み会か何かの際機械科出身の前課長に「造兵学科って何を勉強するんですか?」「何故今の課長は計測制御が専門なんですか?」と質問したことがある。
分かってきたことは、造兵学科とは(軍用機、軍艦を除く;これらは航空工学科、船舶工学科の領域)兵器の研究・開発・生産を担当する技術者を養成するコースであること、そこで艦砲・大砲(高射砲を含む)・魚雷や電子兵器に不可欠な制御技術を学んだことなどである。そして当時(戦前に入学)そこは軍民に引く手数多、たいそう人気のある学科であったこと、従って競争も激しかったこと(つまり成績優秀者が目指す学科)、を知らされた。私はさらに聞いてみた「戦時中の需要に応ずるために、学生を増やすことはなかったんですか?」(この質問の背景には高度成長をうけて文部省が理工系学部の拡充を打ち出していたことにある)。「東大に第二工学部(千葉)を作り、ここにも造兵学科を設けた。いや第二工学部そのものが戦争のために設立されたと言っていい」「そんな学部があったんですか!」これが第二工学部の存在を知ることになった端緒である(両課長とも本郷出身のようだったが)。
軍事オタクとしては印象的な話。それからこの学部に注意していると(殊更踏み込んで調べるほどの関心はなかったが)、80年代から90年代にかけて技術評論家として売れっ子だった唐津一氏が雑誌か新聞に、自身がここの卒業生であり(電子工学)、伝統に縛られない自由で新技術に挑戦する学風に育てられ、“重厚長大”から“軽薄短小”への変革期にマッチした優秀でユニークな人材が活躍していることを書いていた。また、日経新聞の“私の履歴書”で富士通の山本卓真社長がこの学部出身(終戦により復員し直後に入学)であることを知った。しかし、学部の全容とここで学んだ人達をひとまとめにした本に出会うことは無かった。爾来忘れていた世界が突然現れた。それが本書である。
開学は1942年3月、既に太平洋戦争に突入しているが、準備期間があるので開戦前に歴史は遡る。直接の動機は課長の言にあったように陸海軍からの強い要請にあるのだが、もっと根深いところには、ソ連誕生後の5カ年計画による工業化推進の成功とそれに影響された新官僚や軍部の構想する統制経済実現への高度技術者大量養成ニーズがある。これは他の国公立大、私学や高専も含めた文部行政策として各大学・高専にその具体化を求めるもの、その中で東大の対応策が論じられる。時の総長は海軍造船中将(技術士官の最高位)まで登りつめた平賀譲、当然積極論者である。講座(専門分野と認知され教授以下の陣容が整えられた組織)ひとつ増やすにも容易でない学内政治環境、学部新設はもめにもめるが平賀は強引にこれを進める。このために自身は総長を退く羽目になるが、他学部との妥協もなって開設にこぎつける(特に強硬な反対者は経済学部大内兵衛教授;原案の講座数を減じ、経済学部の講座増を認めさせる)。
学科は;土木工学科、機械工学科、船舶工学科、航空機体学科、航空原動機学科、造兵学科、電気工学科、建築学科、応用化学科、冶金学科の10学科。学科の数は既存の工学部(本郷)と同数(本郷は航空工学科が一つ、代わりに火薬工学科がある)。学生数は420名でこれは本郷(378名)を上回る。場所は東大が寮と総合運動場建設に確保してあった千葉市検見川の土地(現在は千葉大学)。学生の振り分けは成績順に、互い違いに行った(1番本郷、2番千葉、3番本郷というように)。だから第二が下というわけではない。それでも第二学部にまわされた者には不満があったようである。しかし輩出した人材は本郷に劣らない。1971年~1995年上場企業役員数は拮抗している。
設立目的が軍と密接に関わっていたこともあって、戦後早い時期に閉鎖が決まり、1951年3月閉学する(入学は3年前の1948年)。つまり9年間しか存在しなかった学部なのである。その後施設と組織は生産技術研究所に変じ、所在地を六本木、駒場と移して大学院教育研究機関として現在に至っている。
本書は設立の背景、設立具体化準備、各学科教科講義内容や教官陣(大先生は本郷から移りたがらないので、若手登用や外部からの招聘があり、新技術研究・修得に利した)、戦時下の兵器研究、卒業生の活躍状況など、このユニークな学部の全容を概説するもので、昭和(軍事)技術史の知られざる一端をまとめたものとして高く評価できる。
蛇足;本書に依れば大学で造兵学を研究・講義するところはドイツと東大(本郷、千葉)しかなかったとのことである。従って東洋各国からの留学生や陸海軍からの依託学生も多く在学したようだ。
また、教科内容として;実用計算、火砲構造及理論、砲架構造及理論、移動砲架、戦車及射爆兵器、魚雷などの講義があったことが記されている。
なお、造兵学科は戦後名称を精密工学科に変じ今に至る。
3)Hard Choices
英国のEU離脱が決まった。次に予想される国際政治の大変革は米大統領選挙だろう。悪い者とより悪い者の選択、世論調査からはそんな気配すら感じられる。ヒラリーもトランプも嫌悪感の高さが歴代候補者に比べ際立つからだ。本書はそのヒラリー・クリントンの著書である。とは言っても選挙用に書かれたものとは読めなかったし、無論自伝でもない。回顧録と言ったところだろう。
個人的には民主党選出大統領の時代は日本にとってあまり好ましいものではないと若い頃から思っているし(F.D.ルーズヴェルトは最悪)、日本との関係をひとまず置いても、共和党に親しみを感じている。これはビジネスを通じてExxonやIBMに所属した友人が多かった影響かもしれない。だからヒラリーの本など全く関心が無かったのだが、東燃同期で原書をよく読み時々読後にそれらを回してくれる友人が「なかなか面白いぞ」と手渡され読むことになった。
時節柄てっきり選挙用の出版物と思い込み、ななめ読みで飛ばそうと取りかかったが、出だしの独白劇に惹きこまれていった。バラク・オバマとの予備選挙戦に敗れた直後、彼から極秘に会いたいと言ってくる。外から見えないようガラスをコーティングしたミニバンに乗って密会場に出かけると大統領本選挙への協力を求められる。国務長官への伏線はこの時に発したようだが本選挙前、本人は気が付かない。昨日までの敵、簡単に受けられる話ではない。揺れ動く敗者としての心の内が数ページに渡り赤裸々に描かれ、「これは率直な気持ちだろうな~」と感じさせる筆致である。
6部構成の内、「もしかすると選挙用?」と思わせるのは第6部“これからの世界”とエピローグくらい。あとはファーストレディ、上院議員時代を僅かに含むものの大部分は国務長官として処した数多くの国際的事件に関する内容、タイトルの“厳しい選択”は当にこれらのことにマッチした適確なものである。
米国国務長官、おそらく世界で最も多く外交・安全保障上の情報がもたらされ、世界の首脳・要人と会談・交渉を行い、難しい決断を迫られ、注目を浴びるポストだろう。メディアは無論、国務省高官ですら知らされていない裏がどんな出来事にもついてまわる。それらを開示できる範囲で明らかにし、時にはそれらに対する個人的な見解や心情も加えて、外交交渉の場を、臨場感をもって伝える。交渉相手や仲介・調停人の名前のみならず接触の動機、身体的な特徴、所作や人柄まで言及する場面がたびたび出てくるので、見知らぬ人物を身近なものにする(特に女性;皇后、スーチー、メルケル、ブットなど)。
出来事・事件はアフガン、イラク、イラン(核開発と禁輸)、シリア、パレスチナとイスラエル、北アフリカ(アラブの春)、パキスタン(オサマ殺害作戦)など中東・イスラムの紛争がらみが多いが、中国(領土・領海、人権)、ビルマ(軍政と禁輸)、アフリカ諸国(経済援助と腐敗)、ロシア(人権、ウクライナ)、メキシコ(麻薬)、キューバ(国交)、ハイチ(地震)なども取り上げられ、国・地域別に章立てて事件が詳細に語られる。これらの中では、パレスチナ和平交渉(アラブの春で揺れ動くエジプトが仲介者)、国交の無いイランとのチャネル作り、アラブの春後のリビアにおける米国出先機関の襲撃などが、移動中の情報交換や刻々変わる状況、それに基づく指示や決定事項が生々しく描かれ、強く印象付けられた。
また地球環境、エネルギー、失業、人権(特に女性)など国・地域とは別の角度から、国際会議における各国・各人の発言や非公式の場での本音のやり取りなどを整理して第6章にまとめている。
無論、この種の回顧録の常で、自分に都合のよいテーマ・内容で書かれていると推察するが、それでも「難しい仕事を、精一杯こなしてきたんだー」との読後感が残った。今は“より悪い者”よりは“悪い者”が大統領に選ばれることになっても「仕方がないか」との心境である。
本書の訳本が日本経済新聞出版社から「困難な選択」と題して出版されていることを付記しておく。
4)老前整理
私の父は91歳で突然亡くなった。役所・会社勤めを70歳までしていたから、完全リタイア後21年生きたことになる。この間次第に遠出は無理になっていったが、前日まで近くのスーパーに買い物に出かけていたほど元気だった。死後遺品整理で気になったことのひとつに、洗濯屋から返ってきたままのワイシャツの多さがある。捨てるには惜しいほどきちんと仕上げられ、洋服ダンスに収納されていた。カジュアルな服装などなじまない世代の典型、医者通いもスーツ・ワイシャツ・ネクタイ姿だったが、それほど着用頻度が高いわけではないから、おそらく何年も前からのままだった違いない。私は引退後9年になる。ワイシャツは父同様洗濯屋が仕上げたまま、10着以上クローゼットの中にぶら下がっている。最も多い白は葬祭(冠婚は皆無に近い)に年数回着用するだけだから、1,2着あれば十分なのだがなかなか処分出来ない。どうしても「もったいない」という気分になってしまうのだ。書籍はともかく我が家にはそんなものが、子供たちが去った家のあちこちに溢れている。「ボツボツ整理を始めなければ」との思いで本書を購入した。
書店で目に入った言葉は表紙・帯に記された“老”、“捨てる”、“片付ける”である。これらから流行の収納術の本でないことは想像がついた。同じく帯にあった“気力、体力があるうちに”が自身の現状とピッタリと解釈、基本的に死に向けての身辺整理を具体的に指南・例示してくれるものと勝手に思い込んだ。「もしかすると物(ハード)だけではなく、PC応用の中身や友人知人との関係などソフトに関する整理法も書いてあるかもしれない」と。しかし最初の頁を読んで「これはどういうことだ?」となってしまった。そこには「あなたがこれからどういう自分になりたいのか、どういう生き方をしたいのかを考え、何が必要かをあなた自身で決め、不要なものをそぎ落とし、新しい生き方、暮らし方をする、そのための道筋をつけるためのお手伝いをしたい」と書かれている。「新しい生き方、暮らし方?」「それは9年前から始めているぜ」。“老前”を“死前(の元気なうちに)”と早とちりしていたのである。
この本のキーワードは著者の定義するこの“老前”。女性では50代(夫が定年を迎える時期)を想定しており、男性はこれから類推すると60代前後と言うことになる(本書は独り者を含め女性中心に書かれている。理由はセミナーやワークショップへの参加者が圧倒的に女性だからだ)。つまり第2の人生を開始する時期を想定して使われているわけで、確かに「新しい生き方、暮らし方」を考える節目に当たる。しかし、私は68歳で仕事中心の生活を終え、既に“新しい生き方”で9年を過ごしたわけだし、変える気はないので対象外ということになる。とは言っても買ったからには目を通そう。そう思って読めばそれなりに収穫はある。それに“気力、体力があるうちに”には一応該当するのだから。
ありました!介護を必要とする段階になると、ケアーマネジャーは無論、ヘルパーや介護士が他人の物を動かすことに対して大きな制約を受けるのだ。こうなると整理は原則不可能になってしまう。伴侶と共用・共有のものは、両者同意の下に整理する方が精神的なストレスが少ない。子供のものは、彼らに判断を仰ぐ。新しいしい生き方(例えば使用頻度)を基に廃棄の基準を定め、場所や物毎にリストを作り、片付けた後をイメージして、時間をかけて気長にやる。物だけではなくお付き合いの仕方(例えば年賀状、会合)もそれに合わせて整理する。こんな話が、ビジュアルな資料も使って展開される。これらは結構参考に出来そうである。
著者はもともとインテリア・コーディネーター。その後ケアーマネジャーの資格を取り、福祉住環境コーディネーター資格試験(東京都)の講師なども務めるこの道の専門家。最近は地方自治体から講演やセミナー開催の要請が多いようで、そこでの事例(ワークショップ、質疑やアンケートを含む)が本書に反映されており、私の期待とは異なるものではあったが、読む人の環境に応じて「なるほど」と思わせる、“老後”整理のヒントや動機付けが見つけられるような気がする。
因みに“老前整理”は著者によって商標登録されている。
5)大格差社会アメリカの資本主義
参議院は全く不要と思うが、棄権をするのは気が済まないので、各党の選挙公約(決して中身を信用するわけではないが)を見ていいて気が付いた。どこの党も同じ主旨(是正)で“格差”を使っていることである。民進党は公約全体のキャッチフレーズとして“格差是正策へ「分配と成長」”、自民党は正規・非正規雇用の格差是正、共産党は“アベノミックスストップ、格差をただす”を掲げ、社民党と改革は“世代間格差是正”とある。すべてはピケティの「21世紀の資本」に発する、格差ブームに便乗していることは明らかだ。
「21世紀の資本」は全世界で100万部以上売れ、国際的に話題になった。最も売れたのは米国で本来経済学論文だったものが“我らは(貧しい)99%”運動を生起して、政治・社会運動に発展、それが日本にも及んできたわけである。
この論文の理論的問題点は米国を始め諸外国でも「アングロサクソン的(米英、特に米国)資本主義の特異な局面が過大にクローズアップされている」との批判が強く、ピケティも部分的にそれを受け入れているし、来日した際も日本の状況にマッチしていないことを認めていた。しかし、社会不安を煽ることで知名度が上がる書き手やメディアはそれを無視してこれを利用している。
本書はそのような変質した格差の意味を、ピケティ批判に言及しつつ、米国資本主義の依ってきたる特異性、明らかに強欲なところを、米金融界を事例に、“自身の体験を基に”、ただすことを目的に書かれたものである。
著者の経歴を本書の内容から整理すると、東大教養学部卒(経済関連学部でなく、ここで学んだことが純然たるエコノミストとは異なる格差分析につながっているような気がする)、1970年代中頃日本債券信用銀行(現あおぞら銀行)に入行、1980年代同行の国際部門の立ち上げに従事、現地法人(証券ジョイントヴェンチャー)に勤務し米国に10年滞在、その間シカゴ大学経営大学院修了、2000年リーマンブラザース日本法人に移り2年間勤務、その後は経済金融アナリスト、となる。
書かれている内容の大部分は、この滞米10年およびリーマン退職までの間の、米国金融界で体験・見聞した身近なその姿である。JVのつくり方、職種と人材の集め方、処遇の決め方などであり、そこから見えてくるのはトップの法外な報酬とモラルハザードを抑えられない業界を取り巻く怪しげな経営環境である。特に報酬については職位や個人名と具体的な数字をあげて“格差”を目の前に示してくれる。少なくとも公開されている情報から、日本の金融界では考えられない破格の所得額である。ただこれは労働所得でありピケティが提示した単純な理論式:ɤ(資本収益率)>g(経済成長率)とは全く関係がない。
この式を確かめるために、古くからの資産家(カーネギー、ロックフェラーなど)や現代の富豪(ビル・ゲーツ、ウォーレン・バフェットなど)の経年的な資産の変化を分析してみると、創業者は確かに高額の資産を保有するものの、年や世代を経ると確実に収益率は低下しており、この式で資本格差を語ることに欠陥があることを指摘する。つまりピケティ理論から派生した格差問題は、資本所得ではなく労働所得によるものなのだと。その意味で“我ら99%”がウォール街を占拠し、社会改革を訴えたことには、本質的には誤解に基づく行動なのだが、労働所得格差の代表としてウォール街を選んだことは象徴的な出来事だったわけである。
この労働所得格差に着目すると、金融界は別にしても、CEOなど経営トップの報酬が米国労働者は無論、他国経営者に比べ突出していることはがはっきり分かる。それは何故か?著者はここでアメリカ特有の政治思想、リバタリアニズム(自由至上主義)の存在と歴史(米国誕生はこの考え方に基づく)を解説し、格差以上に自由を求める(格差は許容しても自由は失いたくない。政府の機能を最小限に抑えたい;レーガン政権による規制緩和、特に金融業のそれが経営・商品開発・報酬などの制約・慣行を解いてしまった)気風が格差を助長するのだと結論付ける。やはりアメリカは特別な国なのだ。
米国は比較的よく知っている国だと思い込んでいたが、本書で教えられることは、リバタリアニズムを含め多々あった。また、米金融界の細部を窺う驚愕の場面の数々(客観的データに基づく)も瞠目させられた。現代アメリカ理解の一助としてお薦めの1冊である。
6)米軍式 人を動かすマネジメント
ビジネスの世界を去ってから経営書はほとんど手にしない。しかし、オペレーションズ・リサーチ(OR;軍事作戦への数理応用を端緒とする)に長く関わったことから、軍事理論・手法の企業経営応用にはいまでも惹かれるものがある。
米軍の指揮官育成教程に使われている意思決定法OODA(観察・方向付け・決心・実行)を知ったのは、「ランチェスター思考Ⅱ」(2010年、福田秀人著、東洋経済刊)によってである。過度に計画立案(特に数値化)に依存することを戒め、柔軟性・機敏性を重視するその発想に触発されるところが多かった。しかし、その後の展開を見ると、予期したほどこの考え方が話題になることは少なく、適用状況を知る機会もなかった。
6年を経てOODAを全面に出した本書がよく売れていることを知り、その間の普及進展状況と経営における具体的な適用策を期待して購読してみた。
結論を言えば期待はずれであった。OODAとは何か?依って来るところは(歴史的経緯は)?PDCA(計画・実行・検証・修正)との違いは?リーダーは如何にあるべきか?など、OODAを中心にリーダー論を軽妙に紹介する内容で、入門書としては評価できるものの、それ以上のものではなかった。これだけでOODAを適用すれば当に「生兵法は怪我のもと」。特に、終章の前までPDCAを散々批判しておきながら、最後にP(計画立案)を慮ってこれをD(デザイン;問題設定)に置換え、P-OODAやD-OODA(ドゥーダ)なる概念を取って付けたように提示するのはいただけない。これに対し「ランチェスターⅡ」はOODA適用を米陸軍指揮マニュアル全体の中で位置付け、それに加えて軍事理論・経営学などを援用してリーダー(下級、上級を分けて)のあり方を論ずる内容・構成になっており、より本格的な経営指南書の性格を持つ。
本書を読んで収穫だったのは、本文ではなく巻尾に付加されている解説である。これは航空自衛官(航空研究センター)による、純軍事教範としてのOODA誕生・採用の経緯と適用を手短にまとめたもので、この考え方の原典(そして原点)に近いところから語られるだけに、むしろ奥の深さを感じた。
蛇足;本稿は、Amazonのカスタマーレビューに投稿した短評を加筆修正したものである。Amazonの投稿では上記のような読後感から星マークは3個にした(最大5)。私の投稿前にはレビューは1件で星マークは5、平均は4に下がる。すると同じ日にごく短い五つ星のレビューが2点加わった。これで平均点は限りなく5点に戻した。ネット口コミのからくり(サクラ?)を身近に体験することになった。私は興味を惹かれた本を手配する前に、カスタマーレビューをチェックするが、星マークの低いコメントに着目している(必ずしも低いから選ばないということではない。高い点はおおむね総花的評価であるの対して、低いものには一点鋭く突くものが偶にあるからである)。これは書物に限らず、宿泊先や飲食店選びでも同様である。
(写真はクリックすると拡大します)