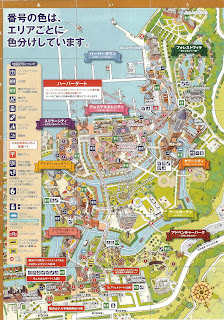21.ラストラン(総括)
3月25日(金)晴れ。本来なら6時半到着が4時間遅れ10時半になった。神戸市内を走るのは、和歌山在住時代を含め、これが初めてだから「早朝の道が空いたうちに」と思っていたが、港湾地区は朝のラッシュ時、大型コンテナーの往来が激しい。六甲アイランドから名神につながる国道43号線(阪神自動車道)魚崎ICまでは専らナビが頼り、西宮ICで名神に入る。ここから吹田JCTまでも未体験ルートなのだが、何かホッとした気分になる。ドライブの楽しみはほとんど無いのだが「これで自宅近くの堀口能見台ICまで自動車道だけで行ける」ことがこの安堵感の因だ。
吹田JCTで中国道と合流すると交通量は一段と増え、全車線流れてはいるものの、車線変更のタイミングが難しいほど。追越車線のひとつ内側を走るようにレーンキープの運転を続ける。草津JCTで新名神に進路を採ると若干空いてくるし、沿線は山がちで風景に変化も出てきて運転にゆとりが持てる。関西と都心を結ぶルートで新東名の静岡県内陸部走行と並んで好きな所だ。
12時土山SAに到着。いつものドライブに比べ少し早いのだが、次のSAは東名阪の御在所と少し遠いので、ここで昼食を摂ることにする。施設は上り下り共通利用形式で食堂も同様。自動販売機で食券を購入する方式なのだが、外国人がガイドに案内されながらそれを求めるので時間がかかる。注文したものの受け取りもそれぞれ(麺類・中華・丼物など)のカウンターの上に番号表示され日本語でアナウンスされるだけなので、日本人でも右往左往している。加えて席の数に制限があるので混乱に拍車がかかる。独占企業の弊害、ここに限らずSA周辺でのビジネスをもっと競争的環境にすべきと痛感させられる。
1時前SA出発。亀山JCTから伊勢湾岸道路を経て豊田東JCTまでは車線数が増えるが分岐も多く進路変更が激しいので最も神経を使うところだ。特に今のナビは古いバージョンなで新東名への最新接続点、豊田東へ誘導してくれない。専ら標示板頼りになるので一層の注意が必要だ。何とか新東名に取り付き浜松SA到着は2時半。ここでおやつと給油(ENEOS)を行う。満タンで16ℓ、往路もここで補給した(19ℓ)だけであとはエッソ・モービル・ゼネラルだったから、他社のガソリンは最小限に抑えられたと言っていいだろう。
このあとのドライブも順調に進み、御殿場JCTで東名に入って、5時10分頃海老名SA着、ここで夕食のため約1時間過ごし、6時50分自宅に帰りつく。これで1983年のアメリカ西部(ユタ、コロラド、アリゾナ)以来の連続長距離ドライブを無事完成させた。日米の道路事情と歳の差(44歳、77歳)を考えると、有森裕子ではないが、我ながら「よく走った!」と褒めてやりたくなるような、タフで充実感のある9日間だった。
総括:
総走行距離;3111km、走行日数;10日、平均走行距離;311km/日、最長走行距離;631.2km/日(自宅→津山)
総燃料消費量;292ℓ、平均燃費;10.65km/ℓ、総燃料費;27,523円
総自動車道通行料(旧道路公団分のみ);55,400円
最も楽しかった走路;ミルクロード→やまなみハイウェイ(熊本・大分)
最も厳しかった(運転技術を要した)走路;豊後竹田→高千穂峡(大分・熊本・宮崎)
最も楽しかった観光地;長崎市
最も満足した宿泊先(価格、情報サービス、利便性など総合して);長崎ヴィクトリアイン
最も美味しかった食事(雰囲気を含む);長崎ホテルモントレーのパスタランチ
最も口にあった酒(風呂上りの生ビールを除く);宮崎Mar&Bar(スペイン料理)の辛口シェリー酒
最も印象深い体験;指宿の砂蒸し風呂
最も心残りなこと;天草→雲仙島伝いルートをスケジュールの関係で走れなかったこと(結果として面白味のない九州道を往復することになった)
私のドライブ旅行目的は先ず走りにある。走りの楽しみを味わうには、ハンドルとアクセル捌きの妙、未知の道と土地、の二つが重要だ。これに第二の目的である観光をどう組み込むか、いつのドライブでも計画段階で調整に苦慮する(楽しいが・・・)。
今回のきっかけは家内両親の墓参(鹿児島)にあるが、今の愛車で、沖縄を除く全都道府県走破を目指している私にとっては未だ走っていない11県の内10県(鳥取・島根・山口と九州7県)を一気に制覇するまたとないチャンスである。未知の土地全てをカバーするルート取りに際して大事なことは、ハンドル捌きにそれなりに挑戦的な道を選ぶことである。第一候補はスケールの大きい阿蘇を巡る道、そして狭隘な山岳道路に挑むため豊後竹田→高千穂峡の林道をトライすることにした。観光は憧れの長崎が最重点、ここだけは連泊でフルに一日代表的な名所を巡る計画にした。結果、総括したように走り甲斐のある道で期待通りの走行を楽しんだし、長崎見物は宿・食を含め全てに満足できた。
おそらく今後これだけの長距離・長期間の連続ドライブ行は無いと思うが、得がたい経験ができた。残るは石川県のみ。いつ、どんな道を走るか?次が疼きはじめている。
-完-
長きにわたり連載閲覧有難うございました。