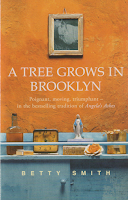<今月読んだ本>
1)アメリカン・ベースボール革命(ベン・リンドバーグ、トラビス・ソ―チック);化学同人社
2)ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー(ブレイディみかこ);新潮社(文庫)
3)インパールの戦い(笠井亮平);文藝春秋社(新書)
4)ラストエンペラー習近平(エドワード・ルトワック);文藝春秋社(新書)
5)A Tree Grows in
Brooklyn(Betty Smith);Arrow Books
6)暁の宇品(堀川恵子);講談社
7)財務省の「ワル」(岸宣人); 新潮社(新書)
<愚評昧説>
1)アメリカン・ベースボール革命
-最新科学で戦うメジャーリーグ、数理分析の先にある物理学・生体工学利用を全公開-
1983年4月下旬Exxonの地域セミナー参加でシドニーに出張した。丁度日本はゴールデンウィーク、セミナー終了後ニュージーランドのクライストチャーチに立ち寄り数日滞在した。日曜の朝貸自転車で市内を巡ると、いたるところで子供たちがラグビーに興じていた。丁度日本の少年野球のように指導者がいて、父母が応援にかけつけている。ラグビーにそれほど馴染みは無くてもオールブラックスの名前は我が国でもよく知られていたから「さすがラグビー王国」とその裾野の広さを改めて実感した。その後Jリーグが誕生、サッカーが盛んになるとTVで中南米の貧しい国々で少年たちが路地でボール蹴りを器用にやっているシーンを見かけ、日本が貧しかった時代我々も原っぱや往来が少ない道路でゴロベースや三角ベースの野球を楽しんだ光景が重なる。どこでも子供の頃から親しんだスポーツは一味違う。
オリンピックではマイナーな種目だが、ワールド杯でいくらラグビー、サッカーが盛んだと言っても、日本人総てがそれなりに興じることが出来るスポーツは野球を置いて他にないだろう。老若男女、贔屓チームの応援、戦略・作戦から個々のプレイヤーの特質、球種・配球まであらゆる角度から、素人でもいっぱし愚説・昧説を披歴しながら試合展開に一喜一憂する。楽しみ方が多様なのだ。先ずは初のオリンピック金メダル、おめでとう!とはいうものの野球は米国の言わば国技、メジャーリーガーの参加しない金メダルはやはり寂しい。最前線の米国野球の今を知りたく本書を手に取った(実は孫が中学の部活で野球部に所属するため話題作りとしてもあるが・・・)。
本書は2003年のベストセラー、2011年映画にもなった「マネー・ボール」(MB)の続編(マネー・ボール2.0)を自称する(著者は異なる。米国ではそれを称する著書が多く出版されている)、米国野球科学に関する最新情報満載の本である。MBはオークランド・アスレチックスのジェネラル・マネジャー(GM)だったビリー・ビーンがモデル。彼自身メジャーリーグ(MLB)のプレイヤーだったが、花を咲かせることなく選手生活を終えスカウトに転じている時、当時のGMが信奉していたセイバーメトリックス(統計学的球団強化策)に惹かれ、自身がGMに昇格するとそれを実施、弱小球団をワールドシリーズの常連に育て上げる。ポイントは出塁率と長打率を組み合わせたOPS(On-base Plus
Slugging;注)と言う新指標である。打者のみならず投手もこれで評価できる(与四球、奪三振、非長打率)。この指標を基に安い選手をトレードで獲得あるいは高額選手を放出し、最少の費用でチーム力を上げていったのだ。ここには従来の選手出身コーチやスカウトとは異なる数理アナリストが重要な役割を果たすことになる。この手法はやがて他球団も知るところとなり、フロントにアナリストを何人も抱えこの面からの戦力は拮抗することになる。では次なる策は?これが本書の内容である。
MBとの違いで本書の概要を紹介すると;
①対象がMBではトレードに依る短期チ-ム力アップに対して、本書は個々の若手選手の育成あるいはベテランの再生に主眼を置いていること。
②動員される“科学”が統計学から、物理学・生体力学・心理学に拡大されていること。例えば、球速と回転数の関係、球種に依る腕への負荷のかかり方あるいはマインドセットと呼ばれる自己暗示(自分の才能は伸ばせるとの確信)の話など。
③最新トレーニング用具に依る、物理面からの解析や生体力学面からの改善・強化策。例えば、エッジャートロニック・カメラと呼ばれる超高速撮影・超低速動画再生装置による分析;球の回転数・速度および回転軸の角度を同時に測定できる装置。
④チームよりは選手個人と野球に特化した訓練・改善コンサルタントの間で進められていったこと(主としてオフシーズン)。現在はほとんどの球団(マイナーを含む)に類似のシステムが導入されている)。
⑤MBではアスレチックス中心だったのに対し、多くのチームや個人が具体的に詳しく解説されていること。
⑥球団経営のみならず監督・コーチ・スカウトの役割変化に言及し、かつて選手実績のあるOBがアナリスト(ほとんどアマチュア野球にも無縁)に取って代わられている“今”を描いていること。
などが挙げられる。
では科学的野球はどうなってきたか。(ホームラン狙いの)フライの増加(アッパースウィング)、それによる三振の増加、出塁を目指す四球の増加。逆にダウンスイング回避に依るゴロの減少。つまり内野手の華麗なプレーやスリリングな走塁の楽しむ機会が少なくなっている。結果、科学はプレイヤーの質を向上させてはいるものの、面白味の無い試合が多くなってきており、著者はルール改定の必要性を示唆する。
我が国に関する点で、データ重視に関して楽天、育成・訓練施設に関してDeNAが出てくる。またメジャーリーガーとして大谷(ただし再生したベテランにホームランを打たれる場面)、ダルビッシュ、菊池雄星がそれぞれ一度だけ顔を出す。
我が国プロ野球の当該分野に全く知識がないが、「さすがアメリカ。ここまでやっているのか!」と思わせる内容。野球談議に蘊蓄を傾けたい向きにはお薦めの一冊である。
著者は二人ともジャーナリスト。他にも野球関係の著作があるようだ。
注;OPS計算ベースは出塁率100%=1、長打率はホームランが4、三塁打が3となり、全打席ホームランならOPSは5となる。通算記録MLBトップはベーブルースの1.164(2位テッド・ウィリアムズの1.116)、NPBでは王貞治の1.080(2位松井秀喜の0.996)、シーズン最高はこれも王;1974年の1.293である。0.9以上はランクA(非常に素晴らしい)と格付けされる。
2)ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー
-日本人の血をひく混血中学生、彼を通して見る英国の多様化世界-
海外旅行記・滞在記は好みの読書ジャンルである。若い頃は、外国へ出かけることなど限られた人の特権、外国に対する憧れから「せめて書物で」と手当たり次第に読んだ。しかし、自身に機会が増えてくると次第に興味の焦点が絞られてくる。現地の人々と同じ目線で日常社会を見ているか否か、文化比較において中庸で冷静な視座を保っているか否か、を特に意識するようになっていく。このチェックポイントを満たすには、どうしても厳しい環境下での長期旅行や生活体験が必要になり、安全面などの制約もあって男性作家に偏りがちになる。例えば、沢木耕太郎や下川裕治などがそれらだ。これに対して女性の紀行文は比較的恵まれた環境からの報告が多く「~では」の“出羽守”調(ある種の上から目線)が気になる。古いところでそれを感じさせなかったのは上智大学外国語学部教授故須賀敦子(1929年生れ)のイタリア物くらいだった。しかし、最近本欄で紹介したヤマザキマリ(「パスタぎらい」2019年8月)や本書の著者の作品(「ブロークン・ブリテンに聞け」2020年12月)を読み、須賀の作品に近い読後感を得(品の良さと言う点において須賀がはるかに優るが)、惹かれるものがあった。そこで文庫本として出版された本書を読んでみることにした。三者の共通点は、いずれも現地の人が伴侶であり、知識人ではあるもののその階級が中流の下くらとうかがえることである。それ故に上から目線が全く感じられないのだ。本書は著者が「地べたの視点」と自称するように、遠い英国の今が即我々の日常とつながる、国際理解の良書である(単行本が2019年本屋大賞受賞)。
著者は1960年福岡の生れ。有数の進学校修猷館高校で音楽に傾倒(前作と併せて推定すると英国のロック)、卒業後は適度に地元で働いては渡英を繰り返し、そこで現在の夫と出会ったようだ。永住を決めたのは1996年、そのころ彼はシティ(金融街)の金融マンだったようだが、リーマンショックでリストラされ、現在は子供の頃から成りたかったダンプカーの運転手をしている。住まいはロンドンの南にある避暑地ブライトン。著者は保育士の資格を取り、しばらく貧民街の託児所勤務の経験がある。本書の主人公は二人の間に生まれた男の子、その子が地元の中学に進んで1年半の学校生活が題材になっている。“イエローでホワイト”は父と母の肌の色、“ブルー”は国語の授業で“ブルー”の意味(色以外の)を問われ“怒り”と回答しバツをもらったことに発する。正解が「気分が沈み込んでいること」であることを知って、ノートの端に本書題名となる言葉を記していたのをたまたま目にしたことからそれを流用する(本が売れると息子が「著作権は僕のものだ!」と冗談を言う。なかなか利発な子であることが窺える)
小学校はカソリック学校(宗教色はあるが公立)に通う(やや遠隔地なので自家用車やバスで通学)。最大の理由は夫がもともとアイルランド出身(カソリック教徒)であることだが、教育レベルが一般の公立校よりは高いことも理由である(市のランキングでトップ)。ここを卒業すると多くの生徒は同様にカソリック系の中学へ進むのだが、父親の反対を押し切って近くの一般中学に入学する。著者はこの学校を「元底辺中学校」と名付け文中頻繁にこれを使うほど荒れていた学校のようだ。“現”でなく“元”なのは現在の英国学校運営制度の下で独自の改善策を進め、底辺から脱出する過程にあることによる。著者らの住まいは伝統的な労働者階級地域に在るのだが(多分タウンハウス;各戸に庭のあるレンガ造りの長屋)、それ以下の人々が住む高層集合住宅のある地域や移民居住区が混在している。ここで生ずる差別・格差はカソリック校とは比較にならず、息子はその中で異次元体験、これを母親(場合によって日本人)の目で、息子の心の内を慮り、英国現代社会を鋭く分析する内容である。
例えば、差別;英国人の労働者階級、同極貧階級、東欧からの移民(白人)、旧植民地からの黒人それに息子のような混血児、その間の差別は単純な人種問題ではなく親の教育や経済レベルの格差も反映して複雑な様相を呈しているのが現実なのだ。息子の親しい友人の一人はハンガリーからの移民、レストラン経営で比較的豊かな家庭、もう一人は貧しく荒れた家庭の英国人、ハンガリー人が英国人を「この貧乏人野郎!」と貶したことから取っ組み合いの喧嘩が始まる。二人とも息子には好意的だから、その悩みは半端ではない。
貧しさの問題;昼食は学校のカフェテリアで摂る。費用は自己負担だが貧しい生徒には一定額のクーポンが付与される。しかし、育ち盛りではこのクーポンだけでは空腹を満たせない。そこで万引きをする。そこから差別・いじめが始まる。夏休みが終わり登校すると話題は「休みはどうだった?」となる。クーポンは休暇中配布されない。「とにかく空腹だったよ」と答える同級生が居たりする(息子はこの間九州に里帰りしているが楽しい思い出話は出来ない)。
授業の内容も興味深い。LGBTQ(Qはクウェッショニング;どちらの性か不明確)では「うちはパパが二人」と話す生徒が居たり、イスラム教徒の女性に行われる性器一部切除が講じられたりし、これがもとで新たな差別が生じたりする。
びっくりしたのは学区内の水泳大会、私立学校と公立学校では泳ぐコースや観客席が異なことだ。「今どきまだこんなことが許されているんだ!」と著者も驚くが、読者も同じ思いになる。私立校の生徒はスウィーミング・スクールに通う余裕もあり圧勝、その中毎夏玄界灘で祖父に鍛えられた息子が一矢報いる。公立校側の騒ぎは尋常ではなく、読んでいる方も目頭が熱くなってくる。
印象的だったのは、シティズンシップ・エデュケーション(公民)の試験で取り上げられたエンパシー(Empathy)と言う言葉だ。日本語訳は「共感・感情移入・自己移入」。シンパシー(Sympathy)と近いが、こちらは「同情・相手を理解すること」とどこか上から目線の“行為・理解”であるのに対し、前者は「相手の身になる」“能力”であると著者は解説、授業では例えとし「他人の靴を履いてみたときの感じ」が挙げられているとある。「なるほど」と納得した。
全編を通じて感じたのは、著者の鋭い観察眼・感性、それを表現する上手さである。今や移民大国に変じた我が国、「地べたベース」の外国・外国人の理解に役立ちそうな話題を大いに楽しんだ。唯一の難点は、大勢に影響はないことだが、私が英ロックに全く通じていないことだった(これは前作も同じ)。
3)インパールの戦い
-敗走した英印軍は2年をかけて反攻準備を進めていた。死屍累々、史上最悪の作戦を敵側から考察する-
今年は太平洋戦争が終わって76年目になる。現在からそれを振り返るのは日露戦争(1905年終了)を1980年に辿るのと同じこと。この頃小説「坂の上の雲」のようなものを別にすれば、既に日露戦争史研究に新たなメスが加えられることは無かったように記憶する。最近めっきり減ったものの太平洋戦争に関しては、それでも新しい視点からの考察が続けられているのは、それだけ我が国近代史への影響が大きかった証左とも言える。「史上最悪の作戦」と揶揄されるインパール作戦、愚将牟田口廉也軍司令官(中将)から前代未聞の師団長の抗命、雨季のジャングルを飢えた敗残兵が彷徨する白骨街道まで汗牛充棟の感があるほど多くの著作が満ち溢れるテーマ、「まだ新しい何かがあるのだろうか?」と、息子より遥かに年少の著者による作品を手に取った。
開戦劈頭マレー半島に上陸した日本陸軍の進軍は翌3月にはシンガポールを落とし、タイに進駐した別部隊はそこを経由して英領ビルマ(現ミャンマー)に向かい首都ラングーン(現ヤンゴン)は1942年3月、中部都市のマンダレーは5月に日本軍が支配するところとなる。英印軍はインド(現バングラデシュ)まで撤退し、東南アジア一帯から駆逐される。余勢をかつてさらにインドに侵攻する案が浮かび上がるが(21号作戦)、現地軍はこれに反対する。その筆頭が牟田口第18師団長だったのだが、それが2年後第15軍司令官になると変心、あの無謀な作戦を強行することになる。
本書の新視点の一つは、この牟田口の変心、専ら彼に責任を帰してきた大本営を含む上部機構の動きの精査および戦史家やノンフィクション作家の定説を見直すところにある。第二の視点は、専ら“インパール作戦”と日本側から戦いを考察しているものが圧倒的に多かったのに対し英印軍側からあの戦いを調査・分析している点である。題名を“作戦”とせず“戦い”としたのはこれによると明記している。これは著者が外務省の専門調査員としてインド・パキスタン・中国に滞在したことが大きく与かっているようだ。第三の新視点は両者の諜報活動(ゲリラ活動を含む)を深耕している点である。
先ず牟田口司令官の責任;無謀な作戦の推進者、充分な兵站を行わず撤退を認めなかった点で彼の責任を問うことでは従来と同様だが、上部の大本営-総軍-方面軍も日本陸海軍全体の劣勢下起死回生を期して彼を督戦したことは確かで、より根源的な責任追及を欠いているとの見解は、従来の著作より強い。1942年攻勢にあったとき彼は師団長、上部の第15軍が可能性を問う程度の進言だったから、兵站を理由に作戦に反対しているが、大本営が出した命令では軍司令官として従わざるを得なかった面がある。
英国の反攻とそれに対する日本軍としての対応;敗走した英印軍は日本軍の攻勢が弱まったためインド東部で態勢を立て直す時間を稼げた。特にインパールの地を巡る兵站線(道路、鉄道)や飛行場の整備に努めた。これが目論み通り戦闘開始で機能することになる。インパールの戦いに先立ち日本軍もビルマ北西部の蒋援ルートを断つべく掃討作戦を実施しているが、少数民族が入り混じる地帯で作戦に難儀していた。加えて英印軍の特殊部隊(Vフォース(グルカ兵中心)、ウィンゲート挺身隊)の活動も活発で、この地方に危機感を募らせていた。
諜報活動;インドは無論ビルマも当時はインド植民地、現在のロヒンギャ問題に見るように、ここは古くから民族・宗教問題がややこしい地域、英国も統治にてこずっており、民俗学者なども動員して状況改善に注力していた。日本も開戦前から中野学校出身者を中心に、F(藤原)機関→岩畔機関→光機関と特務機関を戦線拡大とともに西進させたが、英国に比べ工作能力には各段劣っていた。
以上のようなことから、日本軍の動きは早くから英印軍に正確に把握されており、戦備も整ったところへ、最悪の気象条件下(モンスーン時、世界有数の豪雨地帯)作戦を発動、英印軍の兵站拠点コヒマを一時制圧しながら自軍の兵站が尽き、満を持した英印軍の反攻で敗走を重ねることになる。
本書の読みどころは、この英印軍の動きを彼らの側から多面的に調査分析しそれを日本軍のそれと対比して見せたところにある。それは先にも記したように著者がインド・パキスタンに滞在し、今でも簡単には訪れることが出来ない(ビルマ側からは不可、インド側からも事前許可が必要)地域に何度か足を運び現地調査を行ったことからきている。英国の戦史もよく調べており、その文献の一つに「東のスターリングラード」と記されるほど英印軍にとってもは厳しい戦いであったことが窺える。つまり、上層部はともかく一般兵士は敢闘した戦いだったのだ。その点で“自滅”イメージの強い従来のインパール物とは一味違った読後感だった。
著者は1976年生れ。大学院で国際関係史の修士号取得。外務省専門調査員としてインド・パキスタン・中国に滞在。専門は日印関係史、インド・パキスタン政治史。現在岐阜女子大学特別研究員。
4)ラストエンペラー習近平
-対外同時多発衝突、何故習近平中国は力で相手をひれ伏せようとするのか、出来るのか-
満洲育ちと言うこともあって中国への関心は若い頃から高かった。満洲に関する数々の書物、毛沢東・周恩来の伝記、長征(実態は逃避行)、中国共産党史に関するノンフィクションや訳本など数多読んできたし、最近の中国事情紹介の本もかなりある。これも「いつか彼の地へ」の思いがあるからだ。しかし、その機会はなかなか来なかったし、親しい知人も何度か国際学会で顔を合わせ台湾では二人で故宮博物館に出かけた北京に在る化学工学院(専門大学)の教授くらいしかいない。それもそんなに深くない。やっとチャンスが回ってきたのは2004年第二のビジネスマン人生の中で営業支援を目的に北京に在る国営大企業傘下のエンジニアリング企業を訪れた時一回のみ。一週間足らずの短い滞在で、仕事以外は週末を利用して万里の長城や天安門広場・紫禁城など観光スポットを足早に見て廻ったくらいで、とても「中国を垣間見た」とも言えない体験に終わった。あれから約20年、中国の変貌は世界を驚愕させ、特に安全保障面では周辺国家のみならず欧米さえ警戒心を高めている。その最新事情を世界的な戦略研究者・思想家である著者が著した本書で確認することにした。
先ず鄧小平の改革開放経済を出発点に現代までの中共対外政策を4分割する;チャイナ1.0:対外協調路線を採り中国にもメリット大な時代、チャイナ2.0:リーマンショックへ大型景気浮揚策をとりこれで自信を付ける。揉め事が生じても金で解決できるとの考え方が根付く。チャイナ3.0(これは2.1と言ってもいい):相手を選び弱いと見れば攻撃する。そして習近平下のチャイナ4.0:対外的に同時多発的衝突、何としてでも相手をひれ伏せようとする。南シナ海、東シナ海、インド、オーストラリア、新疆・ウィグル・香港・台湾そして米国。地理的に離れ、経済的に中国重視の欧州さえ5月に中欧投資協定の批准を停止する事態を生じている。ここに一つの戦略的パラドックスがある。強大になるほど揉め事が増加していくのだ。
次に著者の“国力”に関する考え方を披歴する。国力は軍事力、経済力のみならず外交力、政治力さらに「大国的精神」から成るとし、それぞれについて中共の力を分析する。各項の詳細は省くが、トピックスをいくつか取捨し紹介する。軍事力:現中共は過去の最大版図を回復することを目論んでいるが、それは元・清と言う異民族王朝時に広げられたもので漢民族が達成したものではない。漢民族は優秀ではあるが戦争だけは拙劣と断じ、朝鮮戦争やヴェトナム戦争を例に陸軍(解放軍)の弱さを指摘する。また、海軍力は同盟の力が欠かせずそれを欠いていること、さらに近代の海戦において敵国の艦艇を沈めたことのない海軍が勝利した例はないと決めつける。外交力はこの同盟力と不可分、如何に強力なネットワークを構成できるかが決め手となるが、強弱で主従関係を決め対等を認めない中華文明に真のパートナーは存在しない。米国にはクワッド(英国、カナダ、豪州、ニュージーランド)に加え、日本、インドなど強力なパートナーが存在する(ここで韓国には疑義を呈している)。
軍事力、特に海軍力の分析にはさらに踏み込み、現在中共海軍は水上艦艇の強化(空母を含む)に注力しているが兵器体系激変の中でその効果が著しく減じていることを、ミサイル、ドローンや潜水艦の技術発展と対比して語る。ここでは海上自衛隊が保有する12隻の最新通常型潜水艦で100隻以上の中共艦艇を沈められると具体的な数字まで示している。
米中対決の戦場として軍事・外交以外の経済とテクノロジーにも触れ、ここでも中共の弱みを縷々指摘、米国および先進民主国家の優位を論ずる。
ではこのような状況下で何故習近平は自己の権力強化を図り、対外強硬策に出ているのだろうか。ここでは文化大革命下における厳しい下放政策の下で毛沢東を超える“毛沢東思想”信奉者に転じていく過程を述べるとともに、民主的に選ばれなかった指導者・独裁政党の抱える非正統性に対する不安とそれに対する過剰反応、これと相俟って古くからの中国思想「弱者は必ず強者に従う」「従わないのは自分の力が充分でない」ことにその因を求める。ここは著者が中国(特に中共)を喝破したところだろう。
これに対する安全保障上の留意点として;台湾海峡危機、情報・諜報戦(サイバー、スパイ)、それに米国内の政治家の言動を挙げている。後者ではバイデン政権下で登用された元国務長官のジョン・ケリー(交渉人として最もレベルが低い)と元国家安全担当補佐官スーザン・ライス(中共がだましやすい人物)が名指しで取り上げられている。
日本に覚悟を突き付ける一言は是非知っておくべきだろう。「台湾危機が起きた時、『日本が紛争に巻き込まれたくない』と言う姿勢を見せただけで日米同盟は終わる」と。
本書は書下ろしではなく、著者の講演録やインタヴューを基に出版社・訳者が構成したものである。従って場所や時間が異なるものを一つにまとめた不自然さや日本人受け狙いを感じさせるところもある。しかし、日本人の発想にはない我が国を巡る安全保障問題への論説として、触発させられるところが多々あった。
5)A Tree Grows in Brooklyn
-米兵隊文庫の超ベストセラー、そこにあったのは若き戦士たちの戦意を掻き立てたアメリカンドリームだった-
洋書を年に数冊読む。多いのは軍事科学技術とそれと関連する作戦や人物の伝記などだ。エネルギー(特に石油)やときの政治家をテーマにするものがそれに次ぐ。かつてはスパイや狙撃手などを主役とする軍事サスペンス小説も好んで読んだが、最近はこれらを扱う大型書店へ出かける機会がないのですっかりご無沙汰である。そんな読書傾向の中で、後述するように、年頃の少女を主題とする小説を読むことになったことにはそれなりの背景がある。
第二次世界大戦中米兵に読まれた“兵隊文庫”なるものが存在していたことは米大衆文学を題材にした植草甚一や常盤新平のエッセイを通じて知っていた。彼らは放出されたこの文庫から作品のネタを見つけ出していたのだ。それが突然蘇ったのは本欄で紹介した「戦場のコックたち」(2021年1月)、さらに「戦地の図書館」(2021年5月)を読んだからである。特に後者は“兵隊文庫”紹介ノンフィクションと言ってもいい内容で、本書を含む代表的な作品紹介のほか、取り上げられた1200作品すべての発刊時期を含めたリストまで添付されていた。発行総数約1億4千万冊、その中で本書が米兵に「最も好まれた作品」とあったことから「何故だろう?」「是非読んでみたい」となったわけである。
日本語訳は「ブルックリン横丁」、この題名で入手の可否を調べたところ古書として検索にはかかるが、取り扱っているところは見つけられなかった。分かったことは1957年高校生向けに秋元書房と言うところから出ていることくらいだ。さらに調べていくと、原作は1943年発刊、これが「エデンの東」でよく知られるエリア・カザンによって1947年映画化され、そのDVD版を求めることが可能と分かったが、映像は原作の一部に過ぎないのに5千円近くするのでとても買う気にはならなかった。「それでは原書で」と調べていくと米国の出版社ではかなり早い段階で絶版となっているものの英国の書店が新品(版元も英国)を扱っていることを発見、そこから入手したのが手元にある本である。兵隊文庫は大小2種類あり、大は軍服の尻ポケットに小は胸ポケットに収まるとある。兵隊文庫は横長で体裁も異なるから直接比較は出来ないが、届いた本は横125mm縦195mmのペーパーバック、大判の方なのであろうか?厚さは33mm頁数は487、他の本と併読したので読了まで2カ月近く要した。
筋は1910年から1917年秋までの、ニューヨーク・ブルックリンの貧民街に住む聡明だが貧しい少女フランシー(本名はフランシス)の成長物語である。父はアイルランドからの移民二世、母はオーストリアからの移民二世、母の祖父母たちはほとんど英語を解せず、両親もまともな教育を受けていない。父は組合所属の派遣給仕、母は何軒かのアパートを掛け持ちする掃除婦、一歳年下の弟の4人家族だ。父は男前(母はこれに惹かれ友人の彼氏を奪う)で気の良い人だが飲んだくれ、しっかり者の母が一家の大黒柱だ。小学校(中学も一体化)の入学はいじめへの警戒もあり、弟と同時入学にさせられる。しかし、貧民街の学校は定員の倍を超す生徒数、コンクリート普請と生徒たちの荒れ具合はフランシーの夢を打ち砕く。少し離れた職人や商人の地域の学校はレンガ造りで校庭は緑の芝生に覆われている。これも公立校、フランシーは父に頼んで転校を叶える。そこで芽生えるのが文才(国語の授業で高い評価を続ける)。中学卒業後は高校進学を願うが家庭の事情が許さない。卒業前父が寒冷下泥酔し肺炎で死亡、その時母は妊娠中なのだ。フランシーは女工、弟は証券会社(ウォール街)の使い走りで家計を支える。こんなどん底生活の中で、フランシーは、女工レイオフの後得た新聞切り抜きサービスの会社で力量を認められ昇給、何とか弟を高校へ進ませることが出来る。本人の遅れた高校進学、カレッジでの短期教育(卒業資格は得られない)、第一次大戦参戦に依る米国社会の変貌、テレタイプの技術(夜間勤務を希望し、昼間は学校に通う)を習得した彼女は更なる昇給も叶い、母も再婚、養父は経済的にも余裕があり、1917年17歳のときミシガン大学進学に道が開けたところで話は終わる。
読後作者の経歴を調べたところ、この本はほとんど自伝小説であることがわかった。家族構成や居住場所、教育課程などは全く同じ、ミシガン大学ではロースクールに学び弁護士資格を取得、ブルックリンでセッツルメント活動なども行いながら作家としても認められていく。つまり体験に基づくアメリカンドリーム実現の物語なのである。
「戦場のコックたち」の主人公も退屈な田舎町の高校生、第二次世界大戦はそこからの脱却の機会、戦場でこの本を読んで共感をおぼえ、「もし生きて帰れば」と将来に希望をつないだに違いない。読んで超ベストセラーの理由がよく分かった。
6)暁の宇品
-沈められた船だけで7千隻、海軍をはるかにしのぐ陸軍船舶輸送力、広島宇品にあった船舶輸送司令部を初めて明らかにする-
1960年(昭和35年)、大学3年生の夏、私は岩国に在る石油化学工場へ実習に出かけていた。工場側が用意した課題に取り組み簡単な報告書を提出する選択科目の一つである。当時は岩戸景気(日本国開闢以来の意)と言われる高度成長期で理工系学生はどこでも大歓迎、旅費・滞在費は会社負担、この他少額ではあるが日当までもらえる観光旅行と言うのが実態だった。それまで修学旅行で関西(京都・奈良)へは出かけたことがあったものの、それ以西は初めての大旅行である。当時の工場は土曜日もフルタイムだったので休日は日曜のみ、休みは実習生仲間で宮島を含む近くの海で終日過ごすことが多かった。そんなある日曜日広島市まで遠征する計画が持ち上がり、5,6人で出かけることになったが誰もこの地を知る者はいない。幸い、この話を聞きつけた工場幹部が帰省中の子弟を案内役に付けてくれた(1年下のこの人とは彼が同社部長を務めている時再開することになる。また同行した実習生仲間の一人とは今でも交流が続いており、たまに昼食を伴にしている)。原爆記念資料館(本館)を見学した後、何故そうなったか経緯は定かでないものの、市中心部から路面電車に乗り南東部にある宇品と言う港湾地区まで移動、そこで泳いだ後夕方近くのバーでしばし過ごした。若き日の楽しい想い出の地名が付された本書を知り、早速読んでみることにした。
軍都広島、そこに日清戦争時代大本営が設けられ明治天皇の御座所があったこと、ここから大陸に兵士を送り出し帰還兵を迎えたことから世界的にも先進的な検疫所が港の向かいに在る似島に設けられたこと、太平洋戦争でも大陸や南洋諸島あるいはガダルカナルのような激戦地との往来の拠点であったことは社会人になり戦史や戦記を通じて知っていたが、そこが単なる港湾施設ではなく唯一の陸軍兵站コントロールセンターであったことは、本書を読むまで知らなかった。戦後60年を経てまだまだあの戦争に関して知らないことがあるのだ。
陸軍船舶司令部(別称;暁部隊)は陸軍省整備局輸送部と参謀本部第3部(輸送)の二重直轄組織である。最盛時人員数30万人・予算額2億円、この数字は方面軍(その下に軍・師団がある)に等しい。にも拘らず現在までその実態はほとんど知られていない(本書の中でも組織構成が全く説明されない)。太平洋戦争でここが扱った船の内7千隻以上が沈められ、半数以上の船員(軍人・軍属でもない)が死亡している(戦死者:約6万名、戦死率:陸軍20%、海軍16%、船員43%)。
本書は大正8年(1919年)初の陸大卒士官としてここに赴任し、船舶輸送一筋昭和13年(1938年)司令官に登りつめた田尻昌次中将(最終)と最後の司令官佐伯文郎中将(最終)を中心にその活動史を語るものである。両人とも戦後まで存命、特に田尻は6年をかけ全10巻の「船舶輸送作戦の過去と現在」をまとめ防衛庁(当時)に収めたほか膨大な量の手書き自叙伝も残しており、今回これが見つかったことで公的に残らなかった部分の一部が明らかになっている。
先ず、通常他国では海軍の任務である海上輸送を我が国では何故陸軍が直接担当するようになったのか。何と、西南戦争の際海軍が「輸送は我々の仕事にあらず(敵艦艇と戦うのが本務)」とその役割を拒否したからである。これが日露戦争時陸海軍間で正式な協定として発効する。背景には海軍の薩摩、陸軍の長州もあったと言うから驚きだ。陸軍の対策は基本的に民間船舶を船員ごと傭船することで、これが日清戦争から太平洋戦争まで続く方式である。戦線が海外に広がっていくと、船舶の絶対量不足もあって傭船・運用業務は複雑を極め、ここが日本陸軍にとって最も弱いアキレス腱となっていく。加えて、船の問題は輸送ばかりでなく、上陸用舟艇(母船を含む)の開発から最後は特攻艇にまで陸軍海事すべてがここに負わされる。また船舶兵(船舶工兵;上陸用舟艇の運用も行う、船舶砲兵)の養成も独自の機関をもって行う必要が出てくる。
何故宇品が陸軍船舶運用の拠点になったか。日清戦争当時鉄道が広島までしか達していなかったこと、水深が大型船受入れ可能であったこと、周辺に島が多く秘匿が容易であったこと、それにもかかわらず充分な広さの泊地を確保できたこと(200隻程度)、が理由としてあげられている。
さて田尻昌次である。もともとは但馬の裕福な農家であったが父の時代に没落。後援者の助力で横浜の中学を卒業、医師を目指して旧制第三高等学校に合格するが、さらに一家は不幸に見舞われ進学を断念、地元小学校の代用教員をしばらく務めたのち、徴兵検査に際し生徒の段階から給費がもらえる陸士を受験・合格(18期;同期に阿南維幾、山下奉文)、原隊(福知山連隊)勤務などを経て陸大にも合格する(30期)。卒業時参謀本部で外交部門を希望するが、複雑さを増す船舶司令部が陸大卒将校の配属を訴え、歩兵であるにもかかわらずそこにまわされる。その後参謀本部第三部(船舶班)勤務やシベリア出兵によるウラジオストク派遣、第一次上海事件参加などあるものの、船舶司令部司令官まで勤め上げ、昭和14年(1939年)待命(予備役)となる。まさに船舶一筋の将軍なのだ(現在でも防衛省内で「船舶の神様」と尊称されている)。
この予備役入りに問題ありとするのが現代の戦史研究者そして著者の見解である。中将の停限年齢は本来62歳なのだが田尻は57歳で退役している。その少し前に基地の倉庫で不審火があったことでその責任を取らされ諭旨免職と言うのが記録にあるほか自叙伝にも記されている。しかしこの火災は小規模なもので司令官が引責するようなものではない。むしろ二つのことが遠因としてあぶり出される。一つは上海事変上陸作戦に参加した田尻から参謀本部に送られた改善策具申が本部批判と受け取られたこと、また戦線拡大で船舶運用が困難を極め、民間船員犠牲者も急増、これに対する船舶行政改善策(財政、船舶傭船・造船、船員の軍属扱いなど)、を陸軍省上部ばかりでなく関係する他の省(大蔵省・逓信省・厚生省など)にも宛てて意見具申したことが、官僚社会の掟破りと断じられたようだ(他省庁を巻き込むことは現在でもご法度)。この後田尻は陸軍と関係が深い海運会社の責任者として天津に赴任し、戦後無事生還するのだから“塞翁の馬”と言ったところである。
田尻の後短い期間歩兵出身の中将がその任に当たるが(帯に“三人”とあるのはこの人を含む)、それを継いだのが佐伯文郎中将。この人も本来歩兵だが陸大卒業後参謀本部第3部(船舶班)勤務、ここで一時田尻と勤務先が重なっている。昭和14年10月より終戦まで司令官を務める。つまり戦争の真っただ中での責任者、そして原爆投下に遭遇する。開戦前から船舶不足は誰の目にも確かなのに大本営はそれを「ナントカナル」と強行、マレー半島上陸、ガダルカナル救援・撤退、護衛無きシーレーン、日本が兵糧攻めで追い詰められていく中で孤軍奮闘する。最後は原爆投下、中心部にあった軍司令部・師団司令部は壊滅するが離れた宇品の被害は小さい。ここで広島警備担当司令官兼務となり、自身戦闘司令所を中心部に移し、宇品地区にあった多数の小艇を7本の川を交通路として運用、多様な船舶工兵を救護・復旧に当たらせる。食糧・衣料・医薬品は戦地に送るものを放出。爆撃直後上部の指示を待たずに即応したのは、関東大震災時参謀本部勤務を経験したことによる。戦後戦犯に問われ巣鴨に収容されるが、出所後昭和42年(1967年)肝臓がんで死去する。部下だった士官は「残留放射能の影響に違いない」と推察する。
田尻は天津からの引揚後先に述べた「船舶輸送作戦の過去と現在」と今回まで日の目を見ることのなかった「自叙伝」を書き上げ昭和44年(1969年)85歳で他界している。
田尻・佐伯の民間船員に対する待遇改善が実現したのは昭和28年(1953年)、障害年金・遺族年金・弔慰金が支払われるようになる。二人ともそれを見届けることが出来たことはせめてもの慰めとなったのではなかろうか?
著者は1969年広島生まれ、広島大学で学び広島テレビに入社、社会人になるまで広島在住の人である。本書のきっかけは原爆投下候補地として最初から最後まで欠かさず選ばれていたのは広島のみだったことに着目、その理由を探る内に日本陸軍の隘路であるこの地が選ばれたのではないかと宇品を調べ始めたことにある。
私はこの本を読むまで全く知らなかったのだが、ノンフィクション作家としての業績が凄い。それぞれ全く異なる題材で、講談社ノンフィクション賞、新潮ドキュメント賞、大宅壮一ノンフィクション賞を受賞しているのだ!今回の読後感も極めて重厚なものであった。
7)財務省の「ワル」
-「我ら富士山、他は並みの山」と豪語する財務官僚、頂点の事務次官を目指すエリートたちを実名で棚卸しする-
私が学んだ高校は当時としては都立進学校の一つ、毎年現役・浪人を合わせ30人前後が東大に合格していた。同期生の中で入学・卒業総代だったOKM君(同じクラスになったことがないのであまり親しくない)は現役合格組、法学部で学び1961年(昭和36年)大蔵省(現財務省)に入省した。私の父はノンキャリの国家公務員(防衛庁勤務)だったから、多分官報で知ったのだろう「OKM君の配属先(確か理財局)、あまり良いところではないな~」と言う。“良いところ”とは大臣官房、主計局、主税局とのこと。また、局の中でも課に序列があるらしい。この種の話を父とそれまで交わしたことは無かったからびっくりした。「入省時に将来が見えてしまうのか!」と。それから約30年、彼は国税庁次長を最後に退官、地方銀行の常務に天下りした。親しい経済紙の論説委員・編集委員を務めた友人にこのことを話したら「まあ、たいしたことは無いな」と断じられてしまった。父の読みはほぼ当たっていたのである。民間会社にも出世コースはあるが、入社時の配属先からそれが決まることは先ずない。こんな異次元世界、「もしかするとOKM君や同期(同期入省には池田勇人首相の女婿で外相を務めた池田行彦が居る)が出てくるのではないか?」とのぞき趣味もあって本書を手にとった。
財務省キャリアの中で密かに交わされていた言葉に「我ら富士山、他は並みの山」と言うのがあるらしい。1869年大蔵省が発足した時には、出納・租税・監督・通商・鉱山・用度・営繕があり財政と内政を合わせて管掌する強大な役所だったのだから、歴史的に見れば「うべなるかな」の感である。このプライド高い官僚たちのゴールは事務次官。他大学や他学部もたまにあるものの、大方は東大法学部卒である。本書は戦後の代表的事務次官あるいは候補者の人物像を“実名で”語り、運命の転換点を推察するものである。ここで「ワル」とは「ノーパン・しゃぶしゃぶ」の破廉恥役人ではなく「やり手」と言う意味である。
先ず高校だが、戦後しばらくは旧制一高から進んだものが圧倒的に多い、新制になると都立高校優位がしばらく続き、最近は地方の名門公立校に移行しつつある。“富士山”には当然公務員試験上位合格者が集まるのだが、意外なことにトップ合格者で次官まで昇進したのは吉野良彦(1953年入省)一人に過ぎない。また、現役東大合格で順調に進んだ者より、浪人や留年を経験した者の方が多い。さらに、私立進学校からの入省者は多いものの、麻布・灘からいまだ一人も次官は誕生していない(開成からは出ている)。どうも、この手の学校の卒業生は「ワル」に徹しきれないらしい(何となく解る)。
入省後のスタートポイントは父の話の通り。大臣官房の秘書課(官房3課のトップ部署)・文書課・調査企画課(現総合政策課)、主計局・主税局の同様の課に配属された者が確実に重要ポストに就いていく。ゴール間近の昇進ルートは主計局次長(このポストを経ずに次官になった者は戦後皆無)→官房長→主計局長が王道(ただし主税局長・国税庁長官経由も居る)。官房長在籍時不祥事が生じても当事者でない限り軽い懲戒処分程度で済み、有能な人材として温存される(例;オリンピック組織委員会事務局長を務めた武藤敏郎(1966年入省);官房長時代金融検査に関する汚職事件で一旦降格したものの事務次官になりその後日銀副総裁にもなっている)。因みに日銀総裁は次官経験者退職後の最高ポストと位置付けられている。その点では財務官で終わりアジア開発銀行総裁の地位にあった黒田東彦(1967年入省)は異例中の異例。それもあって先輩も含め財務省関係者で彼を支えるものは誰もいないようだ。
「ワル」の代表者として詳しく取り上げられるのは小川是(1962年入省)。大平内閣の一般消費税、中曽根内閣の売上税は挫折するが竹下内閣で3度目の挑戦、1989年消費税法案が成立した背景に首相秘書官であった小川の力が大きかった。竹下は消費税に関する「六つの懸念」を自ら言い出す逆張り戦術を用い、
“懸念”を払拭するシナリオを示して、反対派の空気を“仕方がない”に転じさせ、法案を通すのである。これは小川の発案で主税局と詳細を詰めたものなのである。その小川は国税庁長官を経て1996年次官に登りつめている。
ジャーナリスティックな表現法(週刊新潮連載をまとめたもの)がいささか鼻につくものの、金融庁の分離発足、モリカケに代表される不祥事、国家公務員試験受験者の激減と官僚の不人気(特に早期退職)、一方金融庁で始まった中途採用、理系や女子キャリア処遇問題など、現在の財務省が抱える諸課題にも触れ、人事を核にそれらの現状も理解できた。残念ながらOKM君とその同期はでてこない。「ワル」は居なかったと言うことだろう。“軽い読書”を望む方にお勧めする。
著者は1949年生れ。読売新聞経済部記者を経て現在はフリーランスのジャーナリスト。
(写真はクリックすると拡大します)